

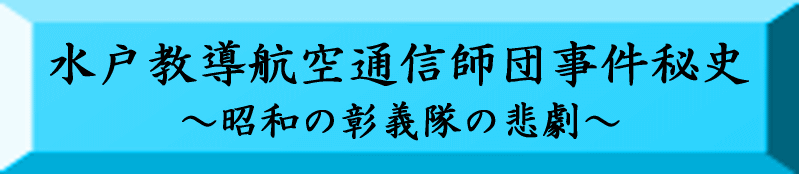
本書は、昭和20年8月中旬に発生した、「水戸教導航空通信師団事件」について、関係者の証言や様々な関係史資料により、今日に至るも詳細が不明確である本事件の実情を明らかにするものです。 大筋においては、既刊の『近衛師団参謀終戦秘史』と重複する内容ですが、その後の追加取材や資料発掘等により、本事件及び皇太子殿下擁立構想に関する分析等関連事項について、更に幅広く且つ深く細部に至るまで詳述されています。 ● ISBN: 978-4-9908114-1-9 ● 分類コード: C3021 ● 規格: 変形A4版、コピー印刷、簡易製本、一部カラー、クリアカバー付き ● 著者: 森下 智 定価(本体価格3,500円+税) 在庫なし
「水戸教導航空通信師団事件」の概要 昭和二十年八月十五日、現在「終戦記念日」と呼ばれるその日の昼、ラジオから雑音混じりの「玉音放送」が流された。その直後から、各地の陸海軍部隊では一様に動揺が拡がっていたが、時間の経過とともに大部分の部隊は粛々と復員に向けて動き始めた。しかし、一部の部隊では徹底抗戦の動きを見せたり、あるいは逆に、規律が弛緩して無断離隊や軍需物資横領が発生したりするなどした。 「徹底抗戦」を叫ぶ陸海軍将兵は全国各地に大勢いたものの、全体的には天皇陛下のご命令に無条件で従う「承詔必謹」が大勢であり、実際に部隊としてある程度まとまって行動したのはごく少数にとどまった。本書で取り上げる、岡島哲少佐率いる水戸教導航空通信師団教導通信第二隊第二中隊による一連の事件(「水戸教導航空通信師団事件」)はその一つである。 八月十五日昼、空襲を避けて茨城県水戸市郊外に疎開していた同師団でも、将兵は集合して「玉音放送」を拝聴したが、これに納得できない岡島少佐ら一部将校は、「東京で終戦阻止のために蹶起した部隊があるらしい。」との情報に基づき、自分たちもこれに合流しようと上京を検討した。岡島少佐の同期生で教導通信第二隊附の杉茂少佐や、中隊の部下である林慶紀少尉は、他の中隊に蹶起参加を呼びかけるが反応は芳しくなかった。また、上官である教導通信第二隊長田中常吉少佐は、当初から首尾一貫して蹶起に反対し軽挙妄動を戒めていた。しかし、岡島少佐は、第二中隊を基幹として臨時の「大隊」を編成し、夜襲訓練を行う等準備を進めた。 翌十六日の日中、教導通信第二隊では非常呼集が行われ、「筑波山に立て籠もる」という名目で「斬込隊」が編成された。また、第二中隊の荒牧健一郎中尉は、以前陸軍戸山学校で知り合った、第八十一師団歩兵第百七十二聯隊大隊長の津田耕作少佐を訪問して蹶起を促したが、結局津田少佐は動かなかった。 十七日未明、林少尉は蹶起に同意しなかった上官の田中少佐を射殺(「田中常吉少佐射殺事件」)、続いて吹田隆一技術中尉を刺突し負傷させた。(「吹田隆一技術中尉傷害事件」)。この後、何者かによる「師団司令部襲撃事件」も発生した。次いで林少尉は中隊長岡島少佐に蹶起の意見具申をした。岡島少佐は慎重に状況判断をしようとしていたところだったが、田中少佐殺害を聞いて速やかな出動を決心した。そして非常呼集をかけて水戸駅まで徒歩で行軍、たまたま入線した仙台行き下り列車を徴発し、機関車を前後付け替えて乗り込み東京に向かった。上京した部隊は鶯谷駅付近で下車、線路伝いに徒歩で上野公園に入った。そして斥候が上野公園内にある東京美術学校(現在の東京藝術大学美術学部)が無人であるのを見つけ、同校に一時進駐(占拠)、ここを拠点として、各人の人脈を辿るなどして各方面に蹶起参加を呼びかけた。これがいわゆる「上野公園占拠事件」の始まりである。また、同じ十七日の朝、対空航測乙種学生長浜田卓志中尉が率いる第二陣が殿軍(しんがり)として師団を出発する際、これを止めようとした吹田技術中尉を松島利雄少尉が射殺したという(「吹田隆一技術中尉射殺事件」)。 一方、「宮城事件(八・一五事件)」に巻き込まれ、八月十五日早朝に東部憲兵隊に一時身柄を保護された近衛第一師団参謀石原貞吉少佐は、当日夕方には師団司令部に原隊復帰していた。十七日、上京した岡島少佐は上木稔夫少尉・青山功少尉を連れて同司令部に赴き、自分が士官候補生だった時に陸軍士官学校本科教練班長だった石原参謀と面会、同参謀から終戦の詔勅が真実であることなどを聞かされた。その後、石原参謀は、東部軍管区司令部の依頼もあって上京部隊に対する撤収の説得を数日にわたり実施した。 十八日朝、水戸に帰る決心をした岡島少佐は、石原参謀から聞いた話を部下に話したが、十九日になって決心が揺らぐこともあった。 その十九日午後、杉少佐と前田中尉は、陸軍航空本部に情勢の確認と諸先輩の意見を聞きに行ったが、水戸で聞いた情報とは全く情勢が異なり、逆に「全員引き揚げなければ武力行使する。」という通告を受けた。驚いた前田中尉は、急ぎ上野に帰隊し、岡島少佐に詳細を報告して部隊の撤収を進言した。その後、夜になって学校正門前のロータリー(低い築山)で「円陣会議」が行われた。この「円陣会議」では、撤収か抗戦続行かの激論が交わされた。会議には教導航空通信師団の将校だけではなく、石原参謀と東京湾兵団参謀中島憲一郎中佐らが加わっていた。やがて、激論の末に撤収することに決したとき、林少尉が拳銃を抜いて石原参謀を突然射殺した。次に、林少尉は銃口を杉少佐に向けたが、それを見た荒牧中尉が咄嗟に林少尉の拳銃を持った右手首を軍刀で斬った。それから林少尉は拳銃で自分の腹部を撃って自決を図り、荒牧中尉が林少尉の介錯をした。また、松島少尉は、宿舎内の部屋で小銃を使って自決した。そして岡島少佐以下の部隊は逐次水戸に引き上げていったのである。 しかし、帰隊後間もなく、浜田中尉が兵舎内で遺書を認めて自決。また、生き残った主要関係者に対する田中師団長の処置は苛烈であり、リーダー格であった岡島少佐・杉少佐と、林少尉を介錯した荒牧中尉が相次いで自決することとなった。 そもそも憂国の至情から始まったこの事件は、最終的に、終戦後多くの有為の人材を失って幕を閉じるという悲劇的な結末を迎えたのである。それは、あたかも、かつて同じ場所で江戸幕府を守るために戦い敗れた彰義隊のようであった。 (『水戸教導航空通信師団事件秘史』序章より一部引用。著者許諾済み)
『水戸教導航空通信師団事件秘史 昭和の彰義隊の悲劇』目次
|
|
![]()
Copyright (C) since 2014 Japanese Society of the History of Imperial Army and Navy
![]()